「思考は整理できているはずなのに、なぜか話が分かりにくいと言われる」「良かれと思って詳しく話すほど相手を混乱させてしまう」など、ビジネスシーンにおいてコミュニケーションの課題を感じている方は少なくありません。特に、専門的な業務に携わる方や思考の速さに自信がある方ほど、自身の能力と他者からの評価にギャップが生まれやすい傾向があります。
「説明が下手なのは頭が悪いからだ」と考えるのは早計かもしれません。実は、優れた思考力や豊富な知識を持つことと、それを分かりやすく伝える能力は別のスキルだからです。
この記事では、なぜ「説明が下手な人」と「頭がいい人」が結びつくのか、その理由や特徴に迫ります。さらに、その特性を単なる弱点ではなく才能の裏返しと捉え、具体的な改善方法を身につけるヒントを提供します。ご自身の思考のクセを理解し、相手に伝わるコミュニケーション術を整え、今日から実践できる小さな一歩を踏み出していきましょう。
- 説明が下手な人と頭がいい人に共通する特徴がわかる
- 説明が下手な人は頭がいいと言われる理由を学べる
- 日々の仕事で実践できる具体的な説明の改善方法が身につく
- 説明下手な特性を強みに変えるための視点が理解できる
説明が下手な人に見られる4つの特徴
- 思考の過程をそのまま話してしまう
- 専門用語や抽象的な言葉を多用しがち
- 聞き手との話の前提を省略してしまう
- 一度に多くの情報を詰め込もうとする
思考の過程をそのまま話してしまう

説明が下手な人の特徴として、結論に至るまでの思考プロセスをそのまま口に出してしまう点が挙げられます。本人にとっては、発見やアイデアが生まれる過程を共有したいという意図があるのかもしれません。あるいは、話しながら思考を整理するクセがついている可能性も考えられます。
例えば、「A案の件ですが、昨日B社の資料を見ていたらCという課題に気づいて、これを解決するにはDという手法があり得るのではないかと考えまして…」といった具合です。しかし、聞き手にとっては話がどこに着地するのかが見えず、「結局、何が言いたいのだろう」「話が長くて要点が分からない」という印象を与えがちです。特に忙しいビジネスの現場では、結論が見えない話は相手の集中力を削いでしまう要因となり得ます。
専門用語や抽象的な言葉を多用しがち

自分の知識レベルを基準にしてしまい、無意識に専門用語や抽象度の高い言葉を使ってしまうのも、よく見られる傾向の一つです。これは「知識の呪縛」と呼ばれる認知バイアス(思い込みや偏見)が関係していると考えられます。一度知ってしまった知識を、相手が知らない状態とは想像しにくいのです。
例えば、ITエンジニアが他部署の人に「このタスクはAPI連携のレイテンシーがボトルネックなので、キャッシュ戦略を再考します」と伝えても、意図は正確に伝わりません。聞き手にとっては、それが外国語のように聞こえてしまうこともあります。
英国政府では、公的な情報発信において平易な言葉の使用を推奨しており、これはビジネスコミュニケーションにおいても重要な視点といえます。(出典:Content design: planning, writing and managing content – Writing for GOV.UK|Government Digital Service)
聞き手との話の前提を省略してしまう
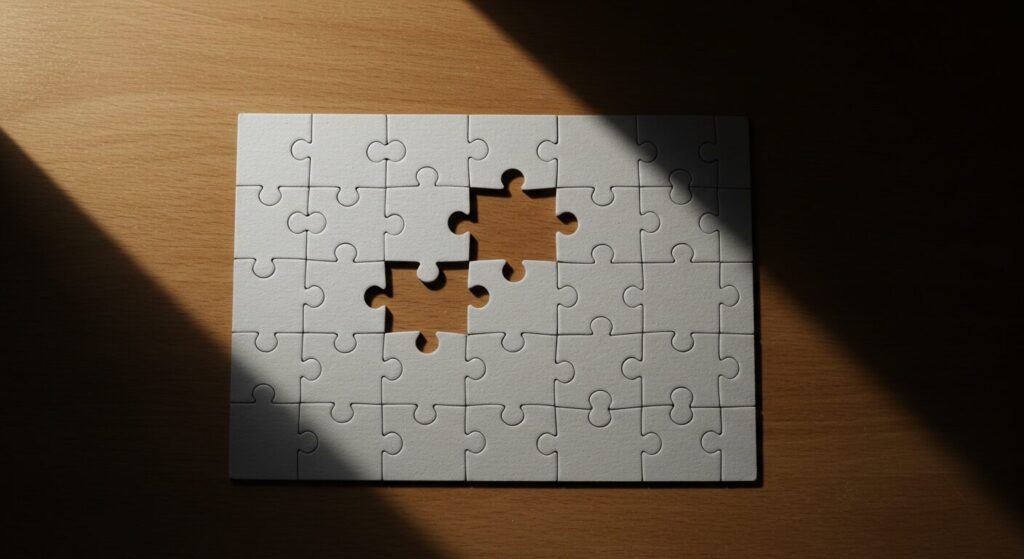
自分の中では当たり前となっている情報や文脈を、相手も当然知っているはずだと無意識に思い込み、説明を省略してしまうことがあります。特に頭の回転が速い人は、思考のスタートラインが相手と大きく異なっているケースが少なくありません。相手の知識レベルを自分と同じか、それ以上に高く見積もってしまう傾向があるのです。
プロジェクトの背景や過去の経緯、登場人物の関係性といった前提情報が共有されていないまま話が進むと、聞き手は話の全体像を掴むことができません。結果として、一つひとつの情報は正しくても、それらがどう繋がるのか分からず、コミュニケーションに齟齬が生まれます。
| 項目 | ダメな例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 説明例 | 例の件、Aさんに確認したらB案で進めることになったので、Cを修正しておいてください。 | 昨日ご相談したXプロジェクトの件です。A部長に確認したところ、コストを優先するB案で進めることになりました。つきましては、B案の内容に合わせて、提案資料のCという項目を修正お願いします。 |
| 評価 | 「例の件」が何を指すか、「B案」がどのような内容か、「なぜ」Cを修正する必要があるのかが不明瞭。 | 前提(プロジェクト名)、経緯(誰に確認したか)、結論(B案で進める)、理由(コスト優先)、具体的な依頼(Cの修正)が明確。 |
一度に多くの情報を詰め込もうとする
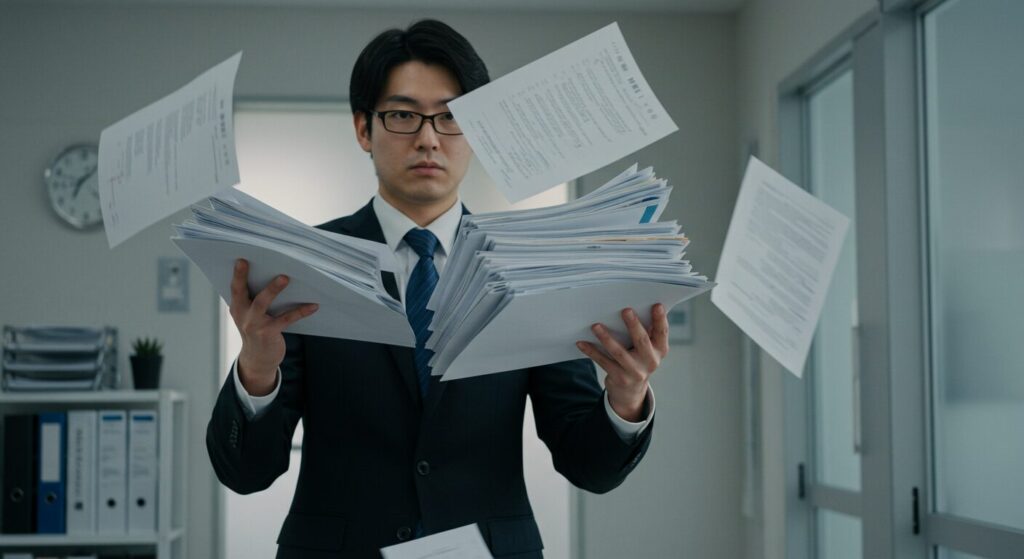
伝えたいことが多いあまり、情報の優先順位をつけられず、一度の会話で全てを伝えようとすることも、説明が分かりにくくなる大きな要因です。本人は親切心から詳しく話しているつもりでも、聞き手側は情報の洪水に溺れてしまいます。
認知心理学の研究では、人間が一度に処理できる情報の量には限りがあることが指摘されています。これはワーキングメモリ(作業記憶)の制約によるものです。
米国国立衛生研究所(NIH)のウェブサイトで公開されている論文によると、一度に保持できる情報の塊(チャンク)は3〜4個程度とされています。(出典:The Magical Mystery Four: How is Working Memory Capacity Limited, and Why?|U.S. National Institutes of Health, 2010-02)
一度に大量の情報を伝えられると、聞き手は重要なポイントを記憶できず、結局何も頭に残らないという事態に陥りやすいのです。説明する際は、伝えるべき要点を3つ以内に絞り込む意識が大切です。
説明が下手な人は頭がいいと言われる理由
- 頭の回転が速いと説明下手になりやすい脳の仕組み
- 豊富な知識が逆に分かりにくさを生む知識の呪縛
- 天才肌の思考法である抽象化と発想の飛躍
- マルチタスクで頭の中が常に情報過多な状態
頭の回転が速いと説明下手になりやすい脳の仕組み
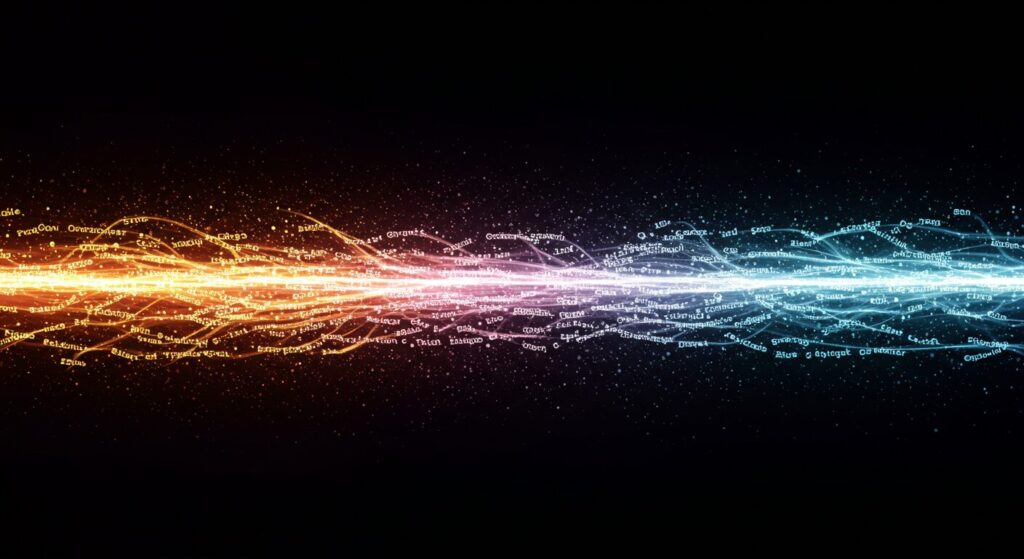
頭の回転が速いことが、説明下手に繋がる根本的な理由の一つに、脳の情報処理速度と言語化の速度のミスマッチが挙げられます。頭がいい人は、脳内で瞬時に複数の情報を結びつけ、結論を導き出すことができます。しかし、言葉でそれを表現するプロセスは、思考のスピードに追いつきません。
その結果、思考の途中経過が大幅に省略され、結論だけが唐突に語られることになります。これは、高速道路を走る車の窓から景色を断片的に説明するようなものです。運転手(話し手)の頭の中では景色が連続的につながっていても、同乗者(聞き手)には、なぜ今その話が出てきたのか、文脈を理解することが困難になります。前述したワーキングメモリの制約も相まって、言語化される情報が断片的になりやすいのです。
豊富な知識が逆に分かりにくさを生む知識の呪縛
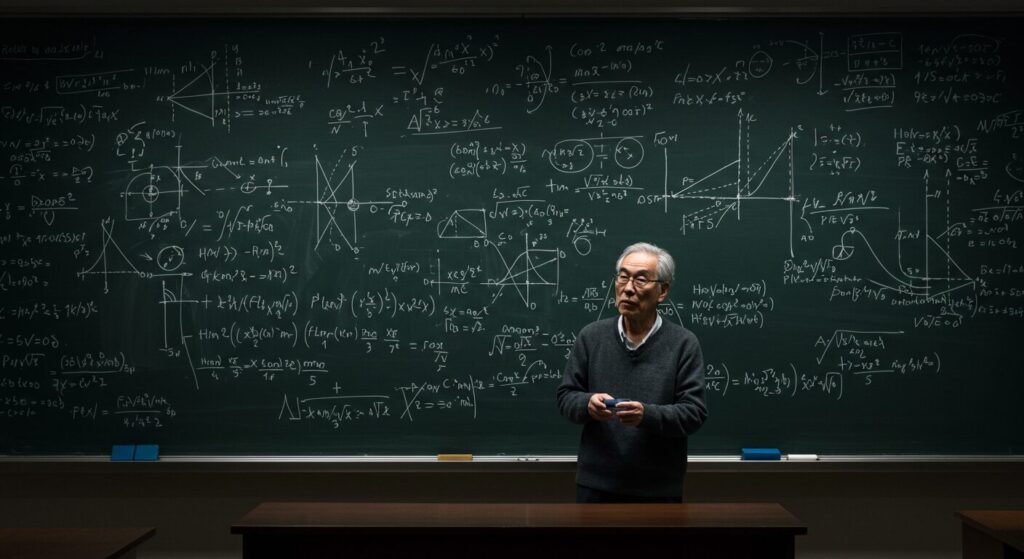
「知識の呪縛」は、頭がいい人が説明下手になる要因を理解する上で非常に重要な概念です。これは、「一度何かを知ってしまうと、それを知らなかった頃の自分を想像できなくなる」という認知バイアスを指します。知識が豊富であるほど、その知識が「当たり前」のものとなり、相手がどのレベルの情報から知らないのかを正確に把握することが難しくなるのです。
例えば、ベテランのシェフが料理の初心者に「適当に火を入れて」と指示するような状況がこれにあたります。シェフにとっては「適当」という言葉に長年の経験に基づいた暗黙知が含まれていますが、初心者には全く伝わりません。このように、豊富な知識を持つ専門家が初心者に何かを教える際に、コミュニケーションの失敗が起こりやすいのは、この知識の呪縛が原因であると考えられます。
天才肌の思考法である抽象化と発想の飛躍

説明が下手な人の中には、いわゆる天才肌と評される人がいます。彼らの思考には、複数の具体的な事象から共通のパターンや本質を抜き出す「抽象化能力」や、一見すると無関係な物事を結びつけて新しいアイデアを生み出す「発想の飛躍力」といった特徴が見られます。
これらの能力はイノベーションの源泉となる一方で、コミュニケーションにおいては分かりにくさの原因にもなり得ます。抽象化された概念は、具体的な事例がないと理解しにくく、また、発想の飛躍が大きいと、聞き手はその論理の繋がりを追うことができません。「AだからCだ」と話している本人の中では「B」というステップが明確に存在していても、その説明が省略されるため、聞き手には話が飛んでいるように感じられるのです。これは決して能力が低いわけではなく、思考の特性に起因します。
マルチタスクで頭の中が常に情報過多な状態
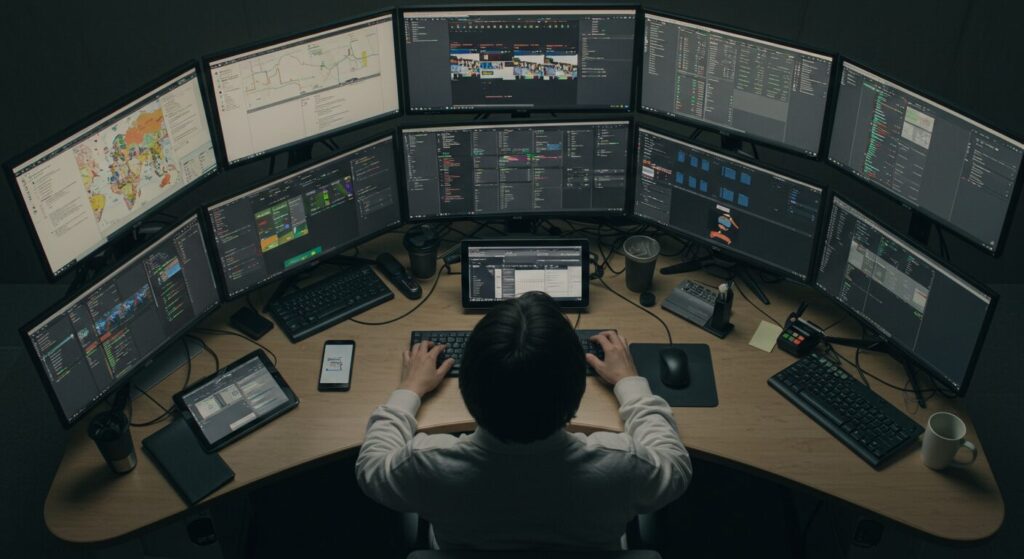
頭がいい人は、常に複数の物事を同時に考えている、いわゆるマルチタスクの状態にあることが多いです。頭の中では常に様々なアイデアやタスクが並行して動いているため、一つのテーマに集中して話すことが苦手な場合があります。
例えば、あるプロジェクトについて話している最中に、関連する別の案件の課題や、全く新しいビジネスのアイデアが浮かんでしまうことがあります。すると、本人は関連しているつもりでも、聞き手にとっては話が急に脱線したように聞こえてしまいます。思考が整理されていないのではなく、むしろ整理すべき情報が多すぎるために、出力する情報を一つに絞りきれないのです。この情報過多の状態が、話のまとまりを欠く原因となります。
説明下手から抜け出す4つの改善方法
- 思考を一度すべて書き出して構造化する
- 結論から話すPREP法を徹底的に意識する
- 聞き手に合わせた言葉選びを練習する
- あえて一文を短く話す訓練をする
思考を一度すべて書き出して構造化する

説明下手を改善するための最初のステップは、頭の中にある情報を可視化し、客観的に整理することです。思考の速さに頼って口頭で伝えようとすると、情報の省略や脱線が起こりやすくなります。まずは話す前に、伝えたいことをテキストや図に書き出してみましょう。
マインドマップや箇条書きツールなどを活用して、思いつくままにキーワードやアイデアをすべて吐き出します。その後、それらの情報をグルーピングし、「何が結論か」「その理由は何か」「補足すべき具体例は何か」といった要素に分類します。このプロセスを経ることで、話の骨格が明確になり、どの順番で何を話すべきかが整理されます。この「書き出す」という一手間が、説明の分かりやすさを飛躍的に向上させます。
伝えたいことや関連情報をキーワード単位で全て書き出す。
書き出した情報を関連性のあるグループに分け、関係性を矢印などで繋ぐ。
「結論」「理由」「具体例」など、話の役割を割り振り、伝える順番を決める。
結論から話すPREP法を徹底的に意識する
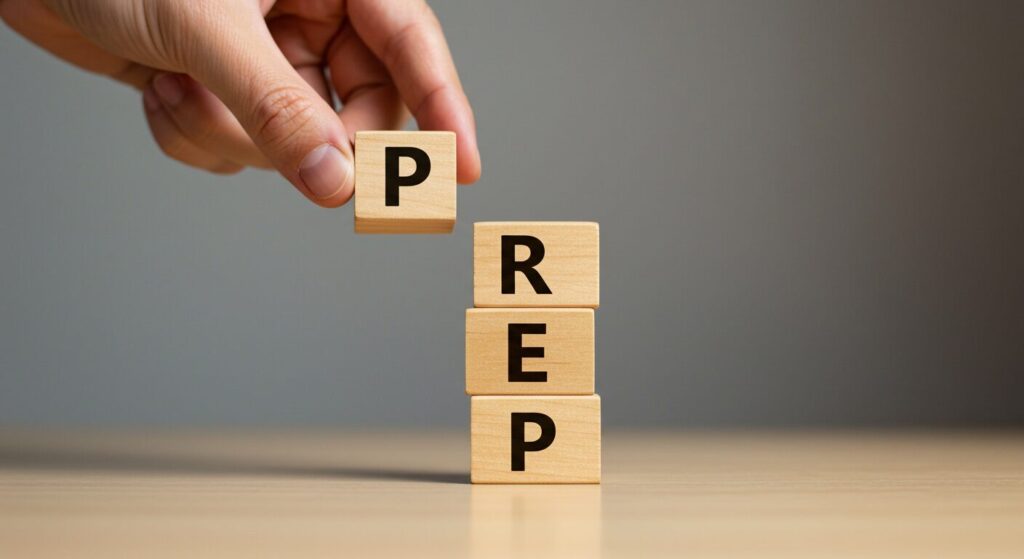
話の構成を整える上で、PREP(プレップ)法は非常に有効なフレームワークです。
Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論を繰り返す)の頭文字を取ったもので、この順番で話を組み立てることで、要点が明確で分かりやすい説明が可能になります。
特にビジネス報告の場面では、「結論から申し上げますと、〇〇です。なぜなら〜」という形で話を始めることを徹底的に意識するだけでも、コミュニケーションは大きく改善します。聞き手は最初に話のゴールを知ることで、その後の理由や具体例を、結論と結びつけながら安心して聞くことができるのです。前述した英国政府の公式サイトが推奨する「ユーザーニーズを先に」という原則は、このPREP法の考え方にも通じるといえます。
PREP法については、理解力がない人に合わせた使い方としても有効です。詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

聞き手に合わせた言葉選びを練習する

分かりやすい説明のためには、相手の知識レベルや立場、関係性を考慮した言葉選びが不可欠です。専門用語を、その分野の知識がない人にも分かるような平易な言葉に言い換えるトレーニングを日頃から行いましょう。
例えば、「この件はエビデンスがファクトベースでクリティカルなイシューです」といった言葉を、「この件は客観的な証拠に基づいており、事業の根幹に関わる重要な課題です」と言い換える練習です。家族や友人に仕事の話をしてみるのも良い訓練になります。デジタル庁が公表しているウェブコンテンツのガイドラインにおいても、国民に情報を伝える際の分かりやすさ(プレインランゲージ)の重要性が指摘されており、これはあらゆるコミュニケーションの基本といえます。(出典:ウェブコンテンツガイドライン(案)|デジタル庁, 2025-09)
| 専門用語・ビジネス用語の例 | 伝わりやすい言葉への言い換え例 |
|---|---|
| アサインする | 担当を割り当てる、参加してもらう |
| エビデンス | 証拠、根拠 |
| バッファを持つ | 余裕を持たせる、予備を用意する |
| コンセンサスを取る | 合意を得る、同意を取り付ける |
あえて一文を短く話す訓練をする

すぐに実践できる簡単なトレーニング方法として、「一文を短く話す」ことを意識するだけでも、説明の明瞭さは大きく変わります。一文が長くなると、「〜で、〜して、〜なので」といった接続助詞が多用され、主語と述語の関係がねじれたり、文の構造が複雑になったりして、聞き手の理解を妨げます。
まずは、意識的に句点「。」で文章を区切るように話す訓練をしてみましょう。例えば、「昨日の会議で決定した件ですが、想定より予算が厳しいことが判明したため、急遽計画を見直す必要がありまして…」と話すのではなく、「昨日の会議で決定した件についてご報告します。想定より予算が厳しいことが判明しました。そのため、急遽計画を見直す必要があります。」と区切るのです。前述した英国政府の公式サイトでも、短い文の使用が推奨されています。これにより、一文ごとの情報がシンプルになり、聞き手の認知的な負担を軽減できます。
説明下手な人は頭がいい?その理由と改善方法まとめ
「説明が下手な人」は、決して「頭が悪い」わけではありません。むしろ、その背景には、速い思考スピードや豊富な知識、優れた抽象化能力といった、頭がいい人ならではの特性が隠れていることが多いのです。
この記事で解説した特徴や原因を理解することは、ご自身のコミュニケーション課題を客観的に捉える第一歩となります。今回紹介した改善方法は、特別な才能を必要とせず、意識と訓練によって誰でも実践できるものです。まずは思考を書き出して構造化することから始めていきましょう。
最後に、ここまでのポイントをまとめておきましょう。
- 思考の過程をそのまま話す傾向がある
- 専門用語や抽象語を多用することが原因である
- 聞き手との話の前提を省略しやすい
- 一度に多くの情報を詰め込むことが要因になり得る
- 思考と言語化の速度の不一致が原因である
- 豊富な知識が「知識の呪縛」を生む原因になり得る
- 抽象化や発想の飛躍は天才肌の思考に表れる
- マルチタスクによる脳の情報過多が影響する
- 改善の第一歩として思考を書き出し構造化する
- 結論から話すPREP法の活用が有効である
- 聞き手のレベルに合わせた言葉選びを意識する
- 一文を短く区切る訓練が大切である

よくある質問
説明が下手なのはトレーニングで改善が見込めますか?
はい、見込めます。多くの場合、能力の問題ではなく思考の整理や伝え方の技術の問題です。思考の可視化やフレームワークの活用といった具体的なトレーニングで改善が期待できます。
周囲に説明が下手で頭がいい人がいる場合どう接すればいいですか?
相手を責めずに、理解を助ける質問をすることが有効です。「要するにどういうことですか」「具体例を一つ教えてください」など、話の要点や具体例を引き出す手助けをしてみてください。
頭の回転が速すぎると言われるのですが関係はありますか?
深く関係している可能性があります。思考のスピードに言語化が追いつかず、話が飛躍したり前提を省略したりする傾向があるため、意識的にゆっくり話す、結論から話すといった工夫が役立ちます。



コメント