ついネガティブな言葉を発してしまい、後から自己嫌悪に陥ることは少なくありません。
一方で、いつも前向きで自信に満ちあふれている人は、物事の捉え方だけでなく、無意識に使う言葉にも共通点があります。
この記事では、自己肯定感が高い人の口癖を7つ厳選し、その言葉が生まれる思考パターンや具体的な特徴を解説します。さらに、日常で実践できる自己肯定感を高める方法も紹介します。ご自身の言葉を見つめ直すきっかけとして、ポジティブな言葉の習慣を取り入れ、より良い毎日への一歩を踏み出しましょう。
- 自己肯定感が高い人が使う7つの口癖とその背景にある思考法がわかる
- 自己肯定感が高い人の根本的な特徴が理解できる
- 日常で自己肯定感を高めるための具体的な方法を学べる
- ネガティブな言葉をポジティブに転換する習慣が身につく
自己肯定感が高い人の口癖7選とその思考パターン
- 「ありがとう」は感謝を伝える基本
- 「面白いね」は好奇心の起点
- 「まあいっか」で自分を許す
- 「どうすればできるか」は未来志向
- 「大丈夫なんとかなる」は不安軽減
- 「おかげさまで」で周囲に敬意を示す
- 「これも経験だね」は学びに転換
「ありがとう」は感謝を伝える基本
自己肯定感が高い人の口癖として、最も基本的でパワフルなのが「ありがとう」です。彼らは特別な出来事だけでなく、日常の些細なことにも感謝を見出す習慣があります。例えば、誰かにドアを開けてもらった時、美味しい食事をいただいた時、あるいは晴れた日の朝といった当たり前に思える瞬間にも、自然と感謝の気持ちを抱きます。
この背景にあるのは、物事のポジティブな側面に光を当てる思考パターンです。常に「ないもの」ではなく「あるもの」に目を向けることで、心の充足感が高まります。「ありがとう」という言葉は、相手に感謝を伝えるだけでなく、自分自身の心を満たす効果も持つのです。
米国の国立衛生研究所(NIH News in Health)でも、感謝を実践することがストレスへの対処能力を高め、前向きな感情を増加させることが示唆されています。(出典:Practicing Gratitude|NIH News in Health, 2019-03)
感謝の言葉を口にすることは、自分と相手の双方に良い心理的影響を与え、良好な人間関係を築くための第一歩といえます。
「面白いね」は好奇心の起点
予期せぬ出来事に遭遇したり、自分とは異なる意見に触れたりした時、多くの人は戸惑いや抵抗を感じることがあります。しかし、自己肯定感が高い人はそういった状況を「面白いね」という言葉で受け止めます。この一言は、未知の状況や他者の考えを脅威としてではなく、学びや発見の機会、すなわち「好奇心の対象」として捉える思考の表れです。
例えば、会議で自分の案とは全く違う意見が出た際に、「なるほど、面白い視点だね」と口にすることで、対立ではなく協調の雰囲気が生まれます。この言葉は、相手の意見を尊重しているというメッセージになると同時に、自分自身の視野を広げるきっかけにもなります。
「面白い」という言葉を口癖にすることで、変化や違いを恐れるのではなく、楽しめるようになります。これは新しいアイデアやイノベーションを生み出す土壌となり、結果的に個人の成長を加速させる重要な習慣といえるでしょう。
「まあいっか」で自分を許す
誰にでも失敗やうまくいかないことはあります。そんな時、自分を責め続けてしまうと、自己肯定感はどんどん下がってしまいます。自己肯定感が高い人は、こうした状況で「まあいっか」という言葉をうまく使います。これは、完璧ではない自分を受け入れ、過度な自己批判を避ける「自己受容」の姿勢から生まれる口癖です。
もちろん、反省が不要というわけではありません。しかし、必要以上に自分を追い詰めず、「今回はうまくいかなかったけれど、仕方ない。次を考えよう」と気持ちを切り替えることが大切です。この「まあいっか」は、失敗を引きずらずに前へ進むための、いわば魔法の言葉なのです。
この言葉を意識的に使うことで、失敗への過度な恐怖が和らぎ、新しい挑戦へのハードルが下がります。自分を許し、再挑戦する力を与えてくれるこの口癖は、しなやかな心を育む上で非常に有効です。
「どうすればできるか」は未来志向
困難な課題や壁に直面した時、私たちの思考は「なぜできなかったのか」という原因追及、つまり過去に向かいがちです。しかし、自己肯定感が高い人は、「どうすればできるか?」と自問します。この問いかけは、思考のベクトルを過去から未来へと転換し、解決策の探求に向かわせる未来志向の思考パターンを象徴しています。
この口癖は、問題を嘆くのではなく、解決すべき課題として捉える主体性を生み出します。「できない理由」を探すのではなく、「できる方法」を考えることで、脳は創造的に働き始め、具体的な行動計画が浮かびやすくなります。
英国の国民保健サービス(NHS)では、認知行動療法(CBT)の一環として、役に立たない思考を捉え直し、より建設的な考え方に変えるアプローチを紹介しています。(出典:Reframing unhelpful thoughts|NHS)
「どうすればできるか」という問いかけは、NHSが紹介する役に立たない思考を捉え直して建設的な考えへ変えるアプローチと方向性が一致します。
この前向きな問いかけを習慣にすることで、課題解決能力を向上させる可能性が高まるでしょう。
「大丈夫なんとかなる」は不安軽減
未来が不確実である以上、不安や心配は誰にでも生じる自然な感情です。しかし、自己肯定感が高い人は、根拠のない不安に心を支配されることが少ない傾向にあります。彼らが口にする「大丈夫、なんとかなる」という言葉は、未来への楽観的な信頼を持つことで、現在の不安を軽減する思考の表れです。
この言葉は、一種の自己暗示(アファメーション)として機能します。口に出すことで、心が落ち着き、物事のポジティブな側面に目を向ける余裕が生まれます。これにより、パニックに陥ることなく、冷静な判断や行動を取りやすくなります。
米国の疾病予防管理センター(CDC)の資料でも、目標達成のために否定的な思考をポジティブなセルフトーク(自分自身への語りかけ)に変えることが推奨されています。(出典:Change Negative Thoughts to Get Motivated|CDC, 2024-05-15)
「大丈夫、なんとかなる」という口癖は、まさにこのポジティブなセルフトークの実践であり、困難な状況でも前向きな行動を促す力となります。
「おかげさまで」で周囲に敬意を示す
物事がうまくいった時や成功を収めた時、その手柄を自分だけのものと考えがちです。しかし、自己肯定感が高い人は「おかげさまで」という言葉を自然に使います。この口癖は、自分の成功は自分一人の力だけではなく、周囲の支えや協力があってこそ成り立つと理解している謙虚な姿勢を示しています。
この言葉は、周囲への感謝と敬意を伝えるパワフルなコミュニケーションツールです。「あなたのおかげです」と伝えることで、相手は自分の貢献が認められたと感じ、より良い協力関係が生まれます。自己肯定感が高い人は、他人を尊重することが、巡り巡って自分自身のためにもなることを知っているのです。
前述したNIH News in Healthの資料でも触れられているように、感謝を言葉や手紙で伝える実践が紹介されており、良好な人間関係づくりに役立つことが示唆されています。
「おかげさまで」という口癖は、チームワークを円滑にし、長期的な信頼関係を築くための重要な鍵といえるでしょう。
「これも経験だね」は学びに転換
失敗は誰にとっても避けたいものですが、それをどう捉えるかでその後の成長は大きく変わります。自己肯定感が高い人は、失敗した際に「これも良い経験だね」と口にします。これは、物事を「成功か失敗か」という二元論で判断するのではなく、すべての出来事を「学びの機会」として捉える思考法(リフレーミング)が習慣化している証拠です。
この言葉によって、失敗は単なるネガティブな出来事ではなく、次に活かすべき貴重なデータへと転換されます。これにより、失敗を過度に恐れることなく、新たな挑戦を続けられるのです。
前述したNHSの資料で紹介されているように、役に立たない考え方を捉え直すことは、精神的な幸福にとって重要です。「これも経験だね」という口癖は、ネガティブな出来事の意味づけを意識的に変え、成長の糧へと転換する強力なリフレーミングの実践といえます。
自己肯定感が高い人の特徴と高める方法
- 自己肯定感が高い人の特徴とは
- 自己肯定感を高める具体的な方法
- NGワードをポジティブに言い換える習慣
- 小さな成功体験を言葉にして積み重ねる
- 触れる情報や環境を意識的に選ぶ
自己肯定感が高い人の特徴とは

自己肯定感が高い人の特徴は、単に自信家であることとは異なります。その核となるのは、長所も短所も含めたありのままの自分を、無条件に受け入れている「自己受容」の姿勢です。彼らは自分の価値を、他人の評価や成功・失敗といった外部の要因に委ねません。そのため、精神的に安定しており、他者からの批判に対しても過度に落ち込むことなく、建設的に受け止めることができます。
厚生労働省のウェブサイト「こころの耳」では、自己肯定感に近い概念としてセルフエスティーム(自尊感情)が解説されており、これが「様々なできごとに対して、前向きな意欲や満足感などを持つことにつながる」とされています。(出典:セルフエスティーム(用語解説)|厚生労働省「こころの耳」)
まさに、自己肯定感が高い人は、この安定した自己認識を土台として、物事に前向きに取り組むことができるのです。
また、自分の感情や欲求を正直に認め、他者との違いを尊重できるため、健全な人間関係を築きやすいのも大きな特徴といえます。
なお、プライドが高く見える人の内面と自己肯定感の関係や、職場での向き合い方については、以下の記事で解説しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

自己肯定感を高める具体的な方法

自己肯定感は生まれつきのものではなく、日々の小さな習慣で育てることができます。
次から紹介する方法は、特別なスキルや時間を必要とするものではありません。口癖を変えることも非常に有効なアプローチの一つですが、それに加えて自分に合った方法を少しずつ取り入れながら、ポジティブな自己認識を育てていきましょう。
NGワードをポジティブに言い換える習慣
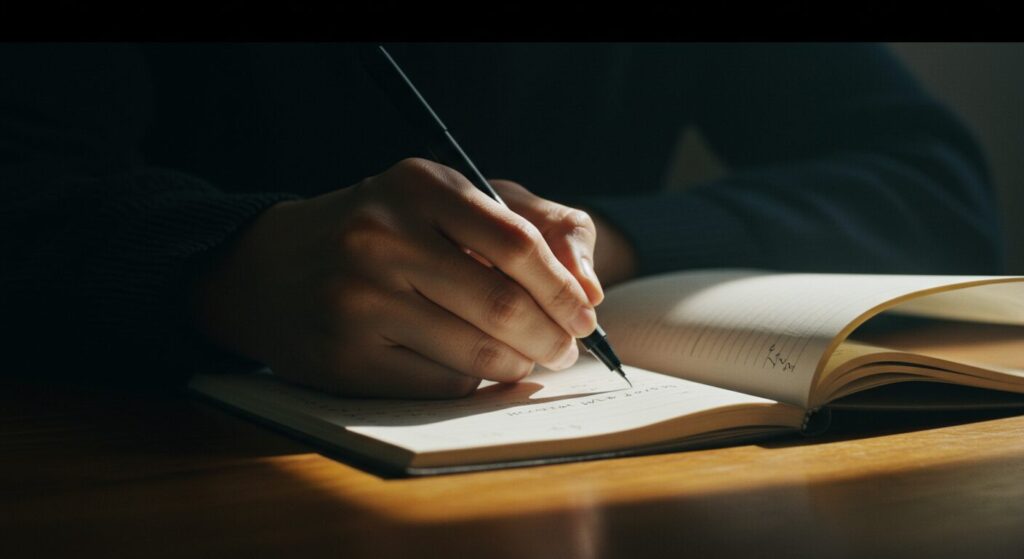
自己肯定感を高めるための第一歩は、無意識に使っているネガティブな言葉、いわゆる「NGワード」に気づき、それをポジティブな言葉に言い換える習慣をつけることです。言葉は思考に大きな影響を与えるため、使う言葉を変えることは、思考パターンを変えることに直結します。
例えば、「でも」「どうせ」「すみません」といった言葉は、自己肯定感を低下させやすい代表的なNGワードです。これらの言葉が口から出そうになった時、意識的に別の言葉に置き換える練習をしてみましょう。前述したCDCやNHSの資料でも、否定的な思考を建設的な言葉に置き換えるアプローチが有効であると示唆されています。
| NGな口癖 | その言葉に隠された心理 | ポジティブな言い換え |
|---|---|---|
| でも… | 否定、抵抗 | なるほど、そういう考え方もあるね |
| どうせ自分なんて… | 諦め、自己卑下 | まずはやってみようかな |
| すみません(謝罪の多用) | 自信のなさ、自己肯定感の低さ | ありがとう(感謝の表現として) |
| ~すべき | 完璧主義、強迫観念 | ~できると良いな |
最初は意識的で大変かもしれませんが、続けるうちに新しい言葉が自然と口から出るようになります。
小さな成功体験を言葉にして積み重ねる

自己肯定感を高めるためには、自分自身で「できた」という感覚、すなわち自己効力感を育むことが重要です。大きな成功を目指す必要はありません。日常生活におけるごく些細な「できた」を自分で見つけ、それを言葉にして認めてあげる習慣が、自己肯定感の土台を着実に築いていきます。
例えば、「今日はいつもより5分早く起きられた」「面倒だったけど、メールの返信をすぐに済ませた」といったことで十分です。大切なのは、その行動を「当たり前」と見過ごさず、「よくやった、私」と心の中や口に出して自分を褒めてあげることです。この小さな成功体験の積み重ねが、「自分はできる」という自信につながっていきます。
- 結果でなく行動を褒める
-
「うまくいった」だけでなく、「挑戦できた」という行動そのものを認めましょう。
- 他人と比較しない
-
あくまでも過去の自分との比較で、「昨日より少しできた」という成長を喜びましょう。
- 具体的に言葉にする
-
「頑張った」だけでなく、「〇〇を最後までやり遂げた」と具体的に褒めることが有効です。
この習慣を続けることで、自己評価が安定し、外部の評価に左右されにくい、しなやかな心が育っていきます。
触れる情報や環境を意識的に選ぶ
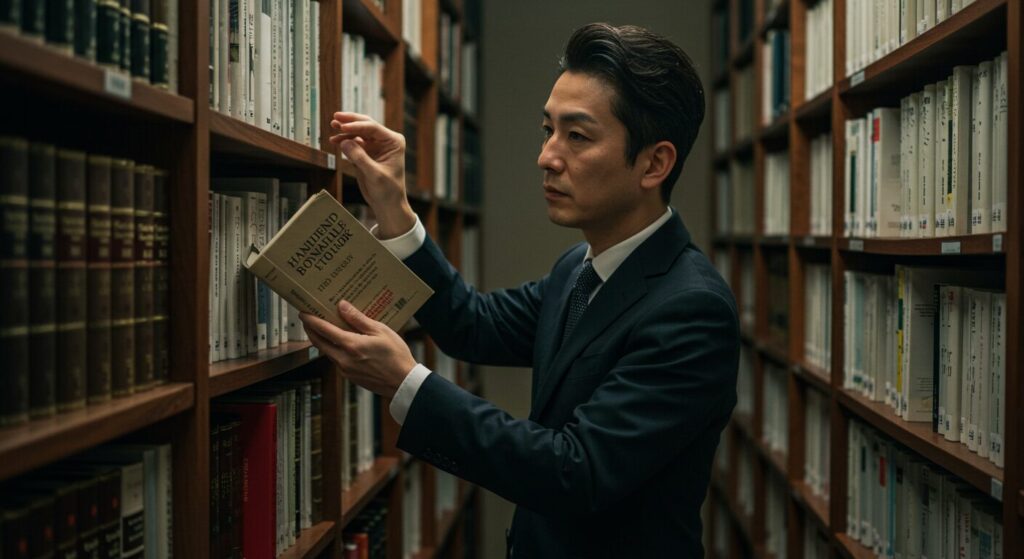
私たちの思考や感情は、日常的に接する人々や情報から大きな影響を受けます。
一人で習慣を変えるのが難しいと感じる場合は、意識的に環境を整えることが自己肯定感を高める上で非常に有効な手段となります。
ポジティブな影響を与えてくれる人との時間
あなたの周りにいる自己肯定感が高い人や、前向きな言葉を使う人と話す時間を意識的に作ってみてはいかがでしょうか。彼らの物事の捉え方や言葉遣いに触れることで、自然とポジティブな思考パターンが身につきやすくなります。逆に、他者を批判したり、否定的な言葉ばかり使う人とは、少し距離を置くことも大切です。自分を守るための環境選びも、自己肯定感を育む上で重要な要素といえます。
インプットする情報を選ぶ
SNSやニュースなど、現代は無意識のうちにネガティブな情報に触れる機会が多くあります。意識的に、自己成長につながる本を読んだり、勇気づけられるような映画を観たり、インスピレーションを与えてくれる内容を発信している人のコンテンツに触れる時間を作りましょう。自分がどのような情報に触れるかを選ぶことは、自分の心の状態をコントロールすることに直結します。
自己肯定感が高い人の口癖と高める方法まとめ
この記事では、自己肯定感が高い人が使う7つの口癖と、その背景にある思考パターン、そして日常で自己肯定感を高めるための具体的な方法について解説しました。
言葉は思考の現れであり、意識して使う言葉を変えることは、自分自身の捉え方や世界の捉え方を変える力を持っています。最初からすべてを完璧にこなす必要はありません。まずは真似してみたいと思う一つの口癖から、日々の生活に取り入れていきましょう。最後に、ここまでのポイントをまとめておきましょう。
- 「ありがとう」で日常の当たり前に感謝する
- 「面白いね」で未知や違いを好奇心で受け入れる
- 「まあいっか」で完璧でない自分を許す
- 「どうすればできるか」で思考を未来に向ける
- 「大丈夫なんとかなる」で根拠のない不安を手放す
- 「おかげさまで」で周囲への敬意と感謝を示す
- 「これも経験だね」で失敗を学びの機会に転換する
- 自己肯定感の核はありのままの自分を受け入れる自己受容である
- 自己肯定感が高い人の特徴は安定した自己認識を持つこと
- 自己肯定感を高める方法はNGワードの言い換えから始めるのが有効
- 日常の小さな成功体験を言葉で認め自己効力感を育む
- 接する人や情報といった環境を意識的に選ぶことが大切

よくある質問
自己肯定感の高い人と一緒にいると疲れてしまいます。
そのように感じてしまうのは、価値観の違いや、無意識に自分と比較してしまうことが原因かもしれません。無理に合わせる必要はありませんが、彼らの言動を観察することで、ポジティブな思考法を学ぶきっかけになることもあります。
自己肯定感が低い人の特徴は?
一般的に、自己肯定感が低い人は自分に厳しく、失敗を過度に恐れる傾向があります。また、他人と自分を比較して落ち込んだり、「どうせ自分なんて」といった否定的な言葉を使いがちです。
周りにネガティブな人が多い場合どうすればよいですか?
他人を変えることは難しいですが、自分の言葉は自分で選べます。まずは自分自身の口癖を意識することから始めましょう。あなたの前向きな言葉が、少しずつ周囲にも良い影響を与えるかもしれません。



コメント