身近な人との関わりの中で、心が消耗したり「自分が悪いのかもしれない」と感じたりすることはないでしょうか。その原因は、無意識のうちにあなたの自己肯定感を下げてくる人の言動にあるかもしれません。こうした人間関係の悩みは多くの人が抱えるものであり、決してあなただけの問題ではありません。
この記事では、自己肯定感を下げてくる人の具体的な特徴5選と、自己肯定感が下がる理由、その背景にある心理を解説します。さらに、職場や友人、家族といった関係別に、今日から実践できる自己肯定感を下げてくる人への対処法までを網羅的に紹介します。自分を大切にするための知識を身につけ、健全な人間関係への一歩を踏出していきましょう。
- 自己肯定感を下げる人の5つの言動パターンがわかる
- 相手の心理や自分がターゲットにされやすい理由が理解できる
- 職場やプライベートで使える具体的な対処法を学べる
- 自分を守り、健全な人間関係を築くヒントが身につく
自己肯定感を下げてくる人の特徴5選
- 常に批判的で否定から入る
- 他人の成功を認めずマウントをとる
- 自分の価値観を一方的に押し付ける
- 無関心な態度で相手の話を軽く扱う
- 罪悪感や劣等感を巧みに刺激する
常に批判的で否定から入る

自己肯定感を下げてくる人の最も分かりやすい特徴は、会話の際に常に批判的で、否定から入る姿勢です。こちらが意見や感想を述べると、開口一番「でも、それは違うよ」「いや、だって」といった言葉で返してくることはありませんか。このようなコミュニケーションが続くと、自分の考えや感覚が間違っているかのような錯覚に陥り、発言すること自体に自信を失ってしまいます。
こうした言動は、相手の意見を尊重する対話ではなく、一方的な論破や間違い探しに近いものです。たとえ相手に悪気がなかったとしても、否定され続けることで少しずつ思考がネガティブになり、自己肯定感はじわじわと削られていきます。
厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、職場におけるハラスメントの一類型として「精神的な攻撃」を挙げています。(出典:ハラスメントの類型と種類|あかるい職場応援団, 最終閲覧日2025-10-13)
人格を否定するような言動や、威圧的な態度で相手を追い詰める行為がこれにあたり、執拗な否定もその一つと見なされる可能性があります。
他人の成功を認めずマウントをとる

他人の成功や努力を素直に認めず、自分の話にすり替えて優位に立とうとする「マウンティング」も、自己肯定感を下げる人の典型的な行動です。
例えば、仕事で成果を出したことを報告すると、「自分が若い頃はもっと大変だった」「そのくらいで満足していてはダメだ」といったように、相手の喜びを削ぐような反応を示します。この行動の背景には、相手を自分より下に置くことで相対的に自分の価値を確かめたいという心理が隠れていると考えられます。
前述した厚生労働省のページで示されている「精神的な攻撃」には、人格を否定する言動やひどい暴言などが含まれます。マウンティングは、相手の達成感を奪い、自信を喪失させることで、間接的に相手の心を攻撃する行為といえるかもしれません。こうした人と一緒にいると、次第に自分の努力や成果を肯定できなくなってしまいます。
自分の価値観を一方的に押し付ける

「あなたのためを思って言っている」「普通はこうするものだ」といった言葉を使い、一方的に自分の価値観や考えを押し付けてくる人も注意が必要です。本人は善意からのアドバイスのつもりかもしれませんが、受け取る側にとっては、自分の考え方や生き方を否定されているように感じられます。
特に、キャリアの選択やライフプランなど、個人の価値観が大きく関わるテーマでこれをされると、自分の決断に対する自信が揺らぎます。健全なアドバイスは、相手の選択肢を広げる手助けになるものですが、価値観の押し付けは相手の選択肢を狭め、特定の方向に誘導しようとする行為です。このような関わり方が続くと、自分で物事を決める力が弱まり、常に他人の顔色をうかがうようになってしまう可能性があります。
無関心な態度で相手の話を軽く扱う

真剣な悩みや大切な話を打ち明けているにもかかわらず、「へぇ、そうなんだ」「気にしすぎじゃない?」といった無関心な態度で話を軽く扱われることも、自己肯定感を大きく損なう原因となります。
一生懸命に言葉を尽くしているのに、相手に響いていないと感じると、自分が軽んじられているような寂しさや虚しさを覚えるものです。
このような態度は、承認欲求が満たされないだけでなく、自分の存在価値そのものに対する不安をかき立てます。前述した厚生労働省のページでは、ハラスメントの類型として「人間関係からの切り離し」も挙げられています。これは、仲間外れにしたり無視したりする行為を指しますが、会話において相手を軽んじる無関心な態度も、心理的な無視や切り離しに近い影響を与える可能性があります。
罪悪感や劣等感を巧みに刺激する

より巧妙な手口として、相手の罪悪感や劣等感を巧みに刺激して、自分の思い通りにコントロールしようとする人がいます。例えば、「あなたがいると本当に助かる」と言って過剰な仕事や要求を押し付けたり、「あなたならできると思ったのに残念だ」と期待をちらつかせて相手を失望させたりするような言動です。
このようなコミュニケーションは、相手に「自分が応えなければならない」「がっかりさせてしまったのは自分のせいだ」と思わせることで、断りにくい状況を作り出します。頼られているようで、実際には都合よく利用されているケースも少なくありません。繰り返し罪悪感を刺激されると、自分に自信がなくなり、「自己肯定感が下がる相手」の要求に応えることでしか自分の価値を見出せなくなってしまう危険性があります。
自己肯定感が下がる理由とその影響
- 自己肯定感が下がる主な理由
- 相手の言動の裏にある劣等感や支配欲
- ターゲットにされやすい人の共通点
- 放置が危険な理由と心身への影響
自己肯定感が下がる主な理由

自己肯定感が下がる理由は、単に相手の言動だけにあるとは限りません。自分自身の物事の受け止め方や、無意識の思考パターンも大きく影響しています。他者からの否定的な言葉を必要以上に重く受け止めてしまう傾向が、ダメージを深刻にする一因となるのです。
例えば、一度の指摘を「自分はすべてにおいてダメだ」と過度に一般化してしまったり、相手の不機嫌を「自分のせいかもしれない」と結びつけてしまったりする思考の癖が挙げられます。こうしたパターンは、相手から受けた小さな傷を、自分の中で大きく育ててしまうことにつながります。過去の経験から「自分には価値がない」といった否定的な自己認識を持っていると、それを裏付けるような言動にばかり無意識に注意が向き、さらに自己肯定感が下がるという悪循環に陥ることもあります。
相手の言動の裏にある劣等感や支配欲

なぜ他人の自己肯定感を下げようとするのでしょうか。その行動の背景には、多くの場合、本人自身の劣等感や強い支配欲が隠されています。自分に自信がなく、ありのままの自分を肯定できないため、他人を批判したり見下したりすることでしか自分の優位性を感じられないのです。相手を自分より下の立場に置くことで、一時的に自分の心のバランスを保とうとしていると考えられます。
また、他人を自分の思い通りにコントロールしたいという欲求が強い人も、こうした行動をとりがちです。相手の自信を奪い、判断力を鈍らせることで、自分への依存度を高め、支配しやすい状況を作り出そうとします。これらの言動は、相手が抱える心の課題の表れであり、決してあなたの価値を正当に評価したものではありません。
ターゲットにされやすい人の共通点

一方で、自己肯定感を下げてくる人のターゲットにされやすい人にも、いくつかの共通した傾向が見られることがあります。これは決して被害を受ける側に非があるという意味ではありません。しかし、自分の傾向を理解しておくことは、今後の対策を立てる上で役立ちます。
例えば、以下のような特徴を持つ人は、相手につけいる隙を与えてしまいやすいといえます。
- 自己主張が苦手で、はっきりと断れない
- 対立を恐れ、相手の機嫌を優先してしまう
- 何か問題が起きると「自分のせいかも」と自分を責めがち
- 他者からの承認や評価を過度に気にする
こうした優しさや真面目さは美点でもありますが、時として自分を守るための境界線(バウンダリー)を曖昧にしてしまう原因にもなります。一緒にいると自己肯定感が下がると感じる相手がいる場合は、自分のコミュニケーションパターンを一度振り返ってみるのもよいでしょう。
放置が危険な理由と心身への影響

世界保健機関(WHO)は、職場におけるメンタルヘルスに関するガイドラインの中で、ネガティブな労働環境が従業員の心身の健康に重大なリスクをもたらすことを指摘しています。(出典:WHO guidelines on mental health at work|World Health Organization, 2022-09)
これは職場に限らず、あらゆる人間関係においていえることです。自己肯定感を下げられる状況を放置すると、様々な悪影響が現れる可能性があります。
具体的には、物事へのやる気が低下したり、他人を信じられなくなったりすることがあります。さらに、常に緊張や不安を強いられることで、不眠や頭痛といった身体的な不調につながるケースも少なくありません。最も懸念されるのは、うつ病や不安症などのメンタルヘルス不調のリスクが高まることです。「自分が我慢すればいい」と考えずに、早めに対処することが極めて重要といえます。
もし、つらい気持ちが続いたり、心身に不調を感じたりしている場合は、一人で抱え込まずに専門家や信頼できる窓口に相談してください。厚生労働省は、働く人々のためのメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」で、電話やSNSで利用できる様々な相談窓口を紹介しています。(出典:相談窓口案内|こころの耳, 最終閲覧日2025-10-13)
自己肯定感を下げてくる人への対処法
- 職場の上司や同僚との上手な距離の取り方
- 友人やパートナーに境界線を伝える会話術
- 親や家族からの影響を和げる考え方
職場の上司や同僚との上手な距離の取り方

自己肯定感が下がる職場において、自己肯定感を下げてくる上司や同僚との関係は特に厄介です。仕事上、完全に避けることは難しい場合が多いでしょう。このような状況では、物理的・心理的に適切な「距離」を取る工夫が有効です。
物理的な距離としては、不必要な雑談を避け、業務上の関わりは報告・連絡・相談といった最低限のものに留めることが挙げられます。心理的な距離を保つためには、相手の言動を個人的な攻撃として受け止めず、「あの人はそういうコミュニケーションスタイルなのだ」と客観的に捉えることが大切です。相手の評価と自分の価値を切り離して考えましょう。
前述したWHOのガイドラインでは、個人の対処だけでなく、管理職へのトレーニングなど組織的な介入の重要性も強調されています。個人の問題として抱え込まず、必要であれば人事部や信頼できる上司に相談することも選択肢の一つです。
| ついやってしまいがちなNG対応 | 心を消耗しないためのOK対応 |
|---|---|
| 相手の批判を真に受けて落ち込む | 「事実」と「相手の意見」を切り分けて聞く |
| 感情的に反論して対立を深める | 一度持ち帰り、冷静に事実確認や対応を検討する |
| 無理な要求でも受け入れてしまう | できないことは理由を添えて丁重に断る |
| 一人で抱え込み、誰にも相談しない | 信頼できる同僚や人事部、外部窓口に相談する |
さらに、プライベートでの上手な距離の取り方については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

友人やパートナーに境界線を伝える会話術

自己肯定感を下げてくる友達やパートナーなど、近しい関係だからこそ自分の気持ちを伝えるのが難しい場合があります。しかし、大切な関係を長く続けるためにも、健全な境界線を引くことは不可欠です。
その際に役立つのが、アサーティブ・コミュニケーションという手法です。これは、相手を尊重しつつ、自分の意見や気持ちを正直に、誠実に伝えるためのコミュニケーションスキルを指します。英国の国民保健サービス(NHS)の公式サイトでも、「自己主張(アサーティブ)」の実践が解説されています。(出典:Raising low self-esteem|NHS, 2023-04)
アサーティブ・コミュニケーションの具体的な方法の一例として、「I(アイ)メッセージ」を用いると、相手を非難せずに自分の気持ちを伝えやすくなります。
「(あなたが)〜と言ったとき」
「私は(〜という気持ちになり)悲しかった」
「だから、これからは〜してくれると嬉しい」
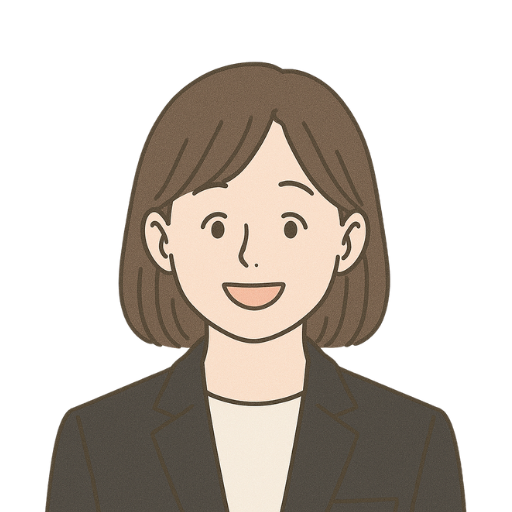
あなたは、いつも私を否定する。
このようなYOUメッセージは、相手を非難する響きになります。
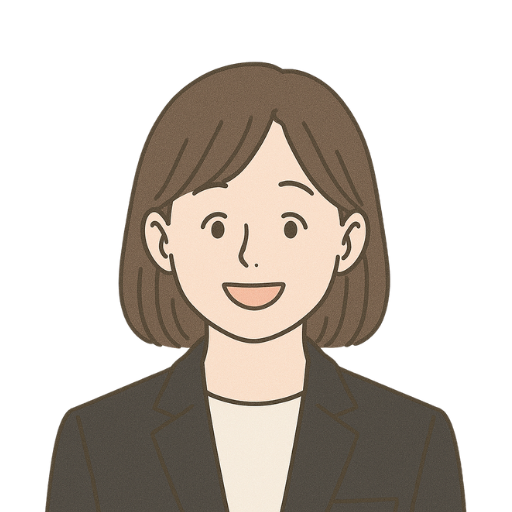
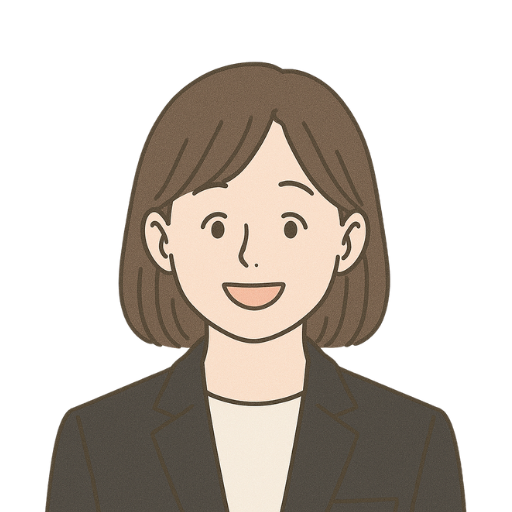
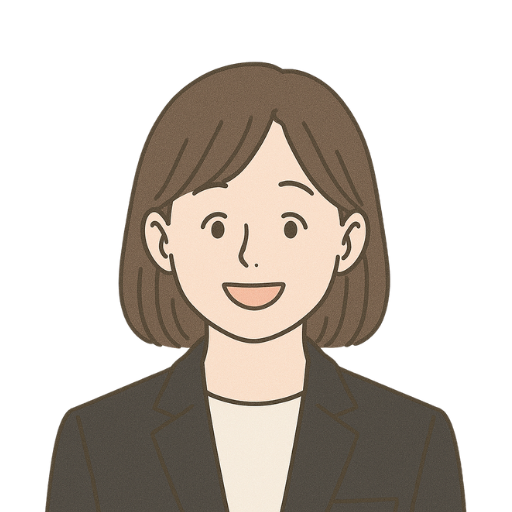
私が意見を言ったときに、「でも」と返されると私は悲しい気持ちになる。
しかし、I(アイ)メッセージなら、相手も受け入れやすくなります。この伝え方を意識することで、無用な対立を避けながら、関係性を改善していくことが期待できます。
なお、アサーティブ・コミュニケーションについては、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。


親や家族からの影響を和げる考え方


自己肯定感を下げてくる親や家族との関係は、最も根深く、対処が難しい問題の一つです。幼少期からの関わりの中で、親の価値観が深く内面化されていることも少なくありません。このような場合、物理的に距離を取ることが難しいケースも多いため、まずは考え方を変えることから始めるのが現実的です。
ここで有効なのが、「課題の分離」という考え方です。これは、「相手の機嫌や評価は相手の課題であり、自分の課題ではない」と切り分ける思考法です。親があなたをどう評価するかは親の問題であり、それによってあなたの価値そのものが決まるわけではありません。親の期待にすべて応えようとするのではなく、「自分は自分、親は親」と考える勇気を持つことが、心理的な自立への第一歩となります。
すぐに考え方を変えるのは難しいかもしれませんが、「これは私の課題だろうか、それとも親の課題だろうか」と自問する習慣をつけるだけでも、少しずつ精神的な距離が生まれ、過剰な影響を受けにくくなっていくでしょう。
自己肯定感を下げてくる人の特徴と対処法まとめ
この記事では、自己肯定感を下げてくる人の特徴から、その背景にある心理、そして具体的な対処法までを解説しました。身近な人の言動によって心が消耗してしまうのは、決してあなたに問題があるからではありません。
特徴や対処法を正しく理解し、自分を守るための境界線を引くことが大切です。すぐに関係を変えることは難しいかもしれませんが、まずは自分を大切にするという意識を持ち、できることから一つずつ試していきましょう。
最後に、ここまでのポイントをまとめておきましょう。
- 自己肯定感を下げる人は常に批判的で否定から入ることが多い
- 他人の成功を認めずマウントをとる行動は優位に立ちたい心理の表れである
- 善意を装い自分の価値観を一方的に押し付けるケースもある
- 無関心な態度は相手の存在価値を揺がせる心理的無視に等しい
- 罪悪感や劣等感を刺激して相手をコントロールしようとする
- 自己肯定感が下がる一因は自身の思考パターンにもある
- 言動の裏には本人自身の劣等感や支配欲が隠れていることが多い
- 自己主張が苦手で相手を優先する人はターゲットにされやすい傾向がある
- 放置すると心身の不調につながる可能性があり早期対処が重要である
- 職場では物理的・心理的な距離を意識的に取ることが有効
- 親しい相手にはIメッセージで自分の気持ちを誠実に伝える
- 親との関係では「課題の分離」を意識し心理的に自立する
- つらいときは一人で抱えず公的な相談窓口を利用することが大切


よくある質問
自己肯定感を下げてくる人からどうしても離れられない場合、どうすればいいですか?
物理的に離れられない場合は心理的な境界線を引くことが大切です。相手の言葉は事実ではなく個人の意見と捉え、自分の価値判断と切り離す練習をしましょう。
相手に悪気がない場合でも関係を見直すべきですか?
相手の意図よりも、自分がどう感じるかを大切にしてください。悪気がなくても自分が継続的に傷つくのであれば、心の健康を守るために関係性や距離感を見直すことをお勧めします。
自分が原因で相手を怒らせているのではと考えてしまいます。
そのように自分を責めてしまうこと自体が自己肯定感が下がっているサインかもしれません。健全な関係はお互いを尊重するものです。一方的にあなたが責められる状況は見直す必要があるでしょう。



コメント