自己肯定感の低さに悩んでいる大人は少なくありません。
そんな自分を変えたくても、大人になってからでは手遅れではないかと不安に感じる方も多いでしょう。
他人と比較して落ち込んだり、失敗を過度に恐れたりするその感覚は、決してあなた一人のものではありません。
多くの方が、過去の経験や思考の癖によって、ありのままの自分を認めることが難しくなっています。
しかし、私たちの心や考え方は、年齢に関係なく少しずつ変化していく柔軟性を持っていると考えられます。
この記事では、自己肯定感の低い大人が手遅れではない理由を、公的機関などの知見を交えながら詳しく解説します。あわせて、自己肯定感が低い原因を整理し、高めるための具体的な方法も紹介します。
まずは、ありのままの自分を受け入れながら、自分のペースで小さな一歩を踏み出してみましょう。
- 自己肯定感の低い大人が手遅れではない4つの理由がわかる
- 自己肯定感が低い主な原因が理解できる
- 自己肯定感を高める具体的な方法を学べる
- ありのままの自分を受け入れながら行動するヒントが得られる
自己肯定感の低い大人が手遅れではない4つの理由
- 大人になっても脳や考え方は変化していく
- 思考の癖は意識的に修正することができる
- 新しい経験が過去の自己認識を上書きしていく
- 大人は環境や情報を自分で選択できる
大人になっても脳や考え方は変化していく
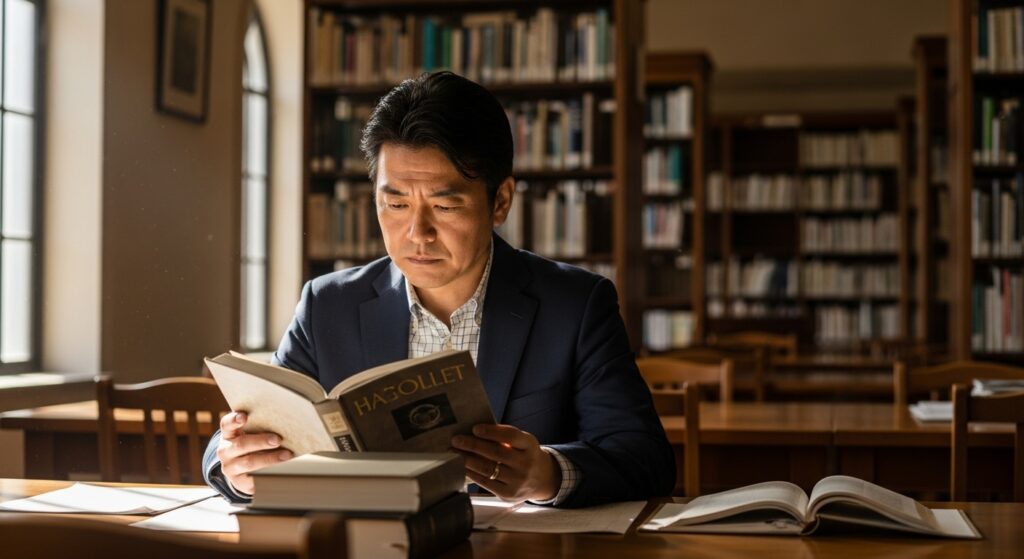
「今さら自分の考え方を変えるのは無理だ」と諦めてしまう方もいるかもしれませんが、何歳になっても脳や考え方は変化していくと考えられています。
これは、私たちの脳には「可塑性」という素晴らしい能力が備わっているからです。
米国の国立医学図書館の一部であるNCBI(National Center for Biotechnology Information)の解説では、脳の可塑性を「内的・外的な刺激に応じて神経系が構造や機能、結合を変化させる能力」と定義しています。(出典:Neuroplasticity|StatPearls / NCBI Bookshelf)
これは、新しいことを学んだり、新しい経験をしたりすることで、脳の神経回路が物理的に変化しうることを意味します。
子供の頃ほど急速ではありませんが、大人の脳も新しい思考や行動を繰り返すことで、そのための新しい神経回路を強化できます。
つまり、自分はダメだと考えるのではなく、自分にもできるという新しい考えを意識して繰り返し持つことで、後者を優位にしていくことが可能なのです。
思考の癖は意識的に修正することができる

長年持ち続けてきた自己肯定感の低さは、生まれつきの性格ではなく、過去の経験から学習した思考の癖であると考えられます。
例えば、何か失敗したときに自動的に「やはり自分は何をやってもダメだ」と考えてしまうのは、生まれつきの性格ではなく、後天的に身についた思考パターンです。
英国の国民保健サービス(NHS)は、こうした「自動的なネガティブ思考」に対処する方法を紹介しています。(出典:Online self-help CBT techniques – Every Mind Matters|NHS)
これは、「考え方に働きかけて気持ちを楽にしていく」という認知行動療法の考え方に基づいています。
自分の考えを客観的に見つめ、それが本当に事実なのか、それとも単なる癖なのかを検証し、より現実的でバランスの取れた考え方に少しずつ修正していくことは、大人になってからでも十分に取り組むことができるといえます。
新しい経験が過去の自己認識を上書きしていく

過去のつらい経験や失敗が、現在の「自分には価値がない」「自分はダメな人間だ」という自己認識を作っているかもしれません。
しかし、その認識は固定されたものではなく、新しい経験によって更新されていく可能性があります。
新しいポジティブな経験は、古いネガティブな記憶と競合する新しい記憶や信念を形成します。
例えば、職場で小さな成功を収める、新しい趣味で仲間から認められる、信頼できるパートナーと出会うといった経験です。
前述したNCBIの解説でも、記憶や神経回路が経験によって再構成されることが示されています。
新しいポジティブな経験を意図的に積み重ねることで、過去のネガティブな自己認識の影響力を相対的に弱めていくことが期待できます。
大人は環境や情報を自分で選択できる

自己肯定感が低い原因が幼少期にあったとしても、大人が子供の頃と決定的に違う点があります。
それは、自分で環境や情報を選べるという点です。
子供の頃は、家庭環境や学校、地域などを自分で選ぶことは困難です。
もしそこが自分を否定する環境であれば、逃れるのは難しいでしょう。
しかし、大人は違います。自分を不当に批判する上司がいる職場なら、転職を考えることができます。
自分を消耗させる人間関係からは、距離を置く選択ができます。
SNSを見て落ち込むなら、そのアカウントをミュートしたり、アプリを削除したりすることも可能です。
この「自己決定権」は、自己肯定感を守り、高めるための強力な武器となり得ます。
自己肯定感が低い原因とは?
- 幼少期の家庭環境や親子関係
- 過去の失敗体験や辛い経験の影響
- 他人との過度な比較
- 完璧主義的な思考の癖
幼少期の家庭環境や親子関係

自己肯定感の低さに、幼少期の経験が影響していることは少なくありません。
特に家庭環境や親子関係は、自己価値観の土台を形成する時期に大きな影響を与えます。
例えば、親から十分な愛情や承認を得られなかった、「あれはダメ」「これもダメ」と過度に批判された、あるいは兄弟や他人と常に比較されて育った場合などです。
条件付きの愛情は、「ありのままの自分には価値がない」という感覚を内面化させる可能性があります。
日本の文部科学省が公表している中央教育審議会の資料では、日本の子どもの自己肯定感が諸外国に比べて低い傾向にあることが指摘されており、その背景に家庭生活での関わりなどが関連していることが示唆されています。(出典:資料3-2「自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育むために」|文部科学省, 2017-06)
過去の失敗体験や辛い経験の影響

幼少期だけでなく、思春期や大人になってからのネガティブな経験も、自己肯定感を低くする原因となり得ます。
受験や就職活動での大きな挫折、仕事での深刻なミス、信頼していた人からの裏切りなど、心に深く残るつらい経験は、「自分は能力が低い」「自分は人から好かれない」といった自己否定的な思い込みを、さらに強めてしまうことがあります。
これらの経験が心の傷として残ると、似たような状況を過度に恐れたり、新しい挑戦を避けたりするようになり、ますます自己肯定感が下がっていくという悪循環に陥ることもあります。
なお、真面目に仕事に取り組んでいるのにミスが多くて悩んでいる方は、「真面目だけどミスが多いのはなぜ?原因と4つの改善法を徹底解説」の記事も参考にしてみてください。

他人との過度な比較

現代社会、特にSNSの普及は、他人との比較を容易にし、自己肯定感をむしばむ大きな要因となっています。
SNSのフィードに流れてくるのは、他人の人生のハイライト(最も輝いている瞬間)ばかりです。
友人の昇進、同僚の結婚、きらびやかな旅行の写真など、他人の成功や幸福な側面と、自分の日常生活を無意識に比較してしまいます。
米国の保健福祉省(HHS)が2023年に公表した資料では、若者を対象にしたものですが、SNSによる社会的比較がメンタルヘルスや自己評価に悪影響を与えるリスクを指摘しています。(出典:Social Media and Youth Mental Health|HHS, 2023)
これは大人にも通じる問題であり、過度な比較は劣等感や焦燥感を生み出し、自己肯定感を低下させる一因になり得ます。
完璧主義的な思考の癖

「常に完璧でなければならない」「失敗は許されない」といった完璧主義的な思考も、自己肯定感を低くする一因です。
完璧主義の人は、全体としてはうまくいっていても、他人にほめられた点ではなく、たった一つのミスや足りなかった部分ばかりを気にして自分を責めてしまいがちです。
その背景には、「結果を出せなければ価値がない」「少しでもミスをしたらすべて台無しだ」と考えてしまうなど、ミスや足りない部分だけに目を向けてしまう思考の癖があります。
これにより、どんなに頑張っても満足感が得られず、常に「自分はまだ足りない」という自己否定感を抱え続けることになります。
| 思考の側面 | 完璧主義 |
|---|---|
| 評価基準 | 「100点か0点か」という二極化思考 |
| ミスへの反応 | 「すべてが台無しだ」と自己否定する |
| 価値の置き方 | 結果や成果だけに価値がある |
なお、完璧主義になってしまう主な原因や具体的な改善法については、「できないくせに完璧主義になってしまう5つの原因と改善法を徹底解説」の記事で詳しく解説しています。
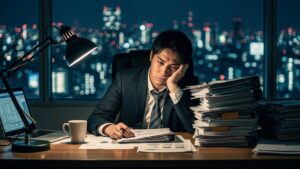
自己肯定感を高める具体的な方法
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 自分を褒める習慣をつける
- ネガティブな感情をポジティブな言葉に変換する
- 他人との比較から距離を置く
- ありのままの自分を受け入れる
- 信頼できる人や専門家へ相談する
小さな成功体験を積み重ねる

自己肯定感を高めるには、小さな成功体験を意図的に積み重ねることが有効です。
自己肯定感が低い状態や、大人になってから自己肯定感が下がる経験をすると、「自分にはできない」という思い込みが強くなりがちです。
この思い込みを覆すには、「自分にもできた」という具体的な経験を重ねていくことが効果的です。
また、英国の国民保健サービス(NHS)でも、自己肯定感を高める方法として、自分の得意なことを見つけたり、新しいことに挑戦したりすることを推奨しています。(出典:Raising low self-esteem|NHS)
小さな目標を立てる
成功体験を積み重ねるためのポイントは、最初から大きな目標を立てないことです。
「資格を取る」といった大きな目標ではなく、「今日は参考書を1ページだけ読む」といった、確実に達成できるレベルの小さな目標を設定します。
ハードルを限りなく低くすることが継続のコツです。
成功体験を書き出す
日々達成した成功体験をノートやアプリに書き出しましょう。
「朝、時間通りに起きられた」「自炊した」「相手の話を遮らずに聞けた」など、どんな些細なことでも構いません。
このリストが、目に見える形であなたの自信の証拠となっていきます。
自分を褒める習慣をつける

小さな成功体験を積み重ねると同時に、自分で自分を認めて褒める習慣をつけることが重要です。
自己肯定感が低い人は、完璧主義的な思考と相まって、できたことがあっても「こんなのは当たり前だ」「大したことない」と過小評価しがちです。
これでは、せっかくの成功体験が自信につながりません。
前述したNHSの資料でも、自己肯定感を高める方法として、「自分に優しくすること」が推奨されています。
これは、失敗した時だけでなく成功した時も同じです。
「今日はよく頑張った」「小さなことだけど前に進んだ」と、意識的に自分にポジティブな声をかけてあげましょう。
他人からの評価を待つのではなく、自分で自分を認めることが自己肯定感の核となります。
ネガティブな感情をポジティブな言葉に変換する

日々の生活でネガティブな感情が湧いてきたとき、それをポジティブな言葉に変換することも有効な手段といえます。
物事の見方や捉え方を変えることで、新たな視点を得る心理学的な手法のことを「リフレーミング」と言います。
無意識のネガティブ思考を、意識的に建設的な捉え方や前向きな言葉に置き換えていくことが、自己肯定感を高めることにつながります。
感情や思考を書き出す
まずは、自分のネガティブな感情や思考を客観的に把握するため、それらをノートやアプリに書き出すことをお勧めします。
前述したNHSの認知行動療法に関するページでも、思考を書き出すことが自分を理解するための重要なステップの一つとして紹介されています。
例えば、「また仕事でミスをした。自分は本当に無能だ。」と書き出すことで、自分の考えを冷静に客観視することができます。
ポジティブな言葉に変換する
自分のネガティブ思考を客観的に把握することができたら、その思考をより現実的でポジティブな言葉に変換します。
| ネガティブ思考 | ポジティブな言葉への変換 |
|---|---|
| ミスをした自分は無能だ | このミスは成長するための貴重な学びだ |
| 緊張してうまく話せなかった | 緊張するのは真剣に取り組んでいる証拠だ |
| 誰も自分をわかってくれない | 伝え方を変えればきっと理解してもらえる |
また、普段からポジティブな言葉を使う人と交流することも、新しい捉え方や言葉の選び方を学ぶ上で大きな助けになります。
さらに、自己肯定感が高い人の口癖について、「自己肯定感が高い人の口癖7選|特徴と高める方法も合わせて解説」の記事で詳しく解説しています。
ポジティブな言葉の使い方を具体的に知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

他人との比較から距離を置く

自己肯定感を高めるためには、他人と比較する習慣から意識的に距離を置くことが大切です。
特に、SNSは過度な比較を引き起こしやすい環境です。
前述した米国保健福祉省(HHS)の公表資料も、社会的比較のリスクについて言及しています。
もしSNSを見て落ち込むことが多いなら、以下のような対策を検討しましょう。
- スマホを見る時間を制限する
- 落ち込む原因となるアカウントをミュートにする
- 一時的にアプリを削除する(デジタルデトックス)
比べるべき相手は、SNS上の誰かではなく、「過去の自分」です。
自分が昨日より少しでも成長できたか、気分良く過ごせたかに意識を向けましょう。
ありのままの自分を受け入れる

自己肯定感を高めるうえで、土台となるのが「ありのままの自分を受け入れる」という自己受容の姿勢です。
これは、セルフコンパッション(自分への思いやり)とも呼ばれます。
自己肯定感というと「自分はすごい」「自分は強い」と思うことだと誤解されがちですが、そうではありません。
自分の長所だけでなく、短所や弱さ、失敗してしまう部分も含めて、それが今の自分だと認めてあげることです。
スコットランドの公式健康情報サービスであるNHS informが公表している資料では、自分への思いやりや完璧でなくてもよいと認める姿勢の重要性が解説されています。(出典:Self-esteem self-help guide|NHS Inform, 2025-08)
失敗して落ち込んだら、まずは「落ち込むのも無理はないよ」「つらかったね」と、親友にかけるような優しい言葉を自分自身にかけてみてください。
信頼できる人や専門家へ相談する

これまでに紹介した方法を試してもうまくいかない、あるいはつらい気持ちが続く場合は、決して一人で抱え込まないでください。
大人になってから自己肯定感が下がることは珍しいことではなく、それは個人の弱さではありません。
信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
また、カウンセラーなど専門家の助けを借りることも、非常に賢明で有効な選択肢です。
前述したNHSの公式ページでも、専門家のサポートを受けることが選択肢として挙げられています。
助けを求めることは、弱さではなく自分を大切にするための強さです。
自己肯定感が低い大人は手遅れ?理由と高める方法まとめ
この記事では、自己肯定感の低い大人が手遅れではない理由や、自己肯定感が低い原因、高めるための具体的な方法について解説しました。
長年染みついた考え方を変えようとすると、不安や戸惑いを覚えるのはごく自然なことです。
ただ、これまでの経験や習慣によって形づくられた思考の癖は、時間をかけて少しずつなら変えていくことができると考えられます。
大切なのは、ありのままの自分を認め、小さな成功体験を積み重ねることです。
そして何より、他人との比較で自分を傷つけるのをやめ、自分自身の心を守りながら、あなたらしいペースで一歩ずつ進んでいくことが重要です。
最後に、ここまでのポイントを振り返りましょう。
- 大人になってからでも自己肯定感は少しずつ高めていくことができる
- 脳の可塑性により、新しい経験を通じて考え方は変化し得る
- 思考の癖は、認知行動療法などで見直しを試みることができる
- ポジティブな経験を重ねることは、過去の否定的な自己認識の影響を弱めるのに役立つ
- 大人は人間関係や情報を選び、自己肯定感を守る環境を整えやすい立場である
- 自己肯定感の低さの背景には、幼少期の家庭環境や親子関係が影響する場合がある
- 受験や仕事の失敗など、心に残るつらい経験は自己肯定感を下げる要因になり得る
- SNSで他人の成功ばかりを見る習慣は、過度な比較を招き自己評価を下げやすい
- 「0か100か」で判断する完璧主義の思考は、自分を否定しやすい土台になる
- 自己肯定感を高める方法として、小さな成功体験を意識して積み重ねることが有効
- 日々のできたことをノートに記録し、自分の前進を見える形にすることが役立つ
- できていない部分ではなく、できた部分に目を向けて自分を褒める習慣を持つことが大切
- ネガティブな考えを書き出し、言葉の捉え方を変えるリフレーミングを実践することが有効
- SNSとの距離を調整し、他人ではなく過去の自分との比較を意識する姿勢が望ましい
- 強さも弱さも含めて今の自分を受け入れ、必要に応じて専門家に相談する姿勢が重要である

よくある質問
自己肯定感を高める簡単な方法は?
まずは、できたことを毎日3つメモすることから始めてみましょう。
「朝起きられた」など、どんなに小さなことでも大丈夫です。
自己肯定感が低いのにプライドは高いのはなぜ?
傷つくのを恐れて、自分を守ろうとする心の防衛反応かもしれません。
ありのままの自分を受け入れる練習をすることで、少しずつ楽になる可能性があります。
自己肯定感が低いのは親のせいですか?
幼少期の環境が影響することはありますが、親のせいだけとは限りません。
原因を探すよりも、今の自分がどうしたいかに目を向けることが大切です。
大人になってから自己肯定感が下がる原因は?
職場での人間関係のトラブルや大きな失敗、SNSによる他人との比較などがきっかけで、一時的に下がってしまうことがあります。



コメント