仕事や勉強、あるいは日常生活の中で、できないくせに完璧主義になってしまう自分に苦しさを感じていませんか?
この矛盾した状態は、失敗を恐れて行動に移せないケースや努力しているのに理想とのギャップで苦しむケースから成り立ち、主な原因として、理想の高さや他人の評価を気にしすぎているということが考えられます。
この記事では、できないくせに完璧主義になってしまう5つの主な原因を整理し、 それぞれに対応する具体的な改善法について、海外の公的機関の知見を交えながらわかりやすく解説します。
まずはご自身の思考や原因を客観的に理解し、完璧主義から抜け出すための小さな一歩を踏出していきましょう。
- できないくせに完璧主義になってしまう5つの原因が理解できる
- それぞれの原因に対応した具体的な改善法を学べる
- 完璧主義の悪循環から抜け出すヒントが得られる
- 行動のハードルを下げる実践的な方法を知ることができる
できないくせに完璧主義になってしまう原因とは?
- 高すぎる理想と現実のギャップ
- 失敗を極度に恐れている
- 他人の評価を気にしすぎている
- 能力不足への不安と自己防衛の心理
- オーバーシンキングと二極化思考
高すぎる理想と現実のギャップ

できないのに完璧を求めてしまう背景には、高すぎる理想と現実のギャップが存在します。
これは、自分の現在の能力やリソース(時間や環境)を客観視する前に、「こうあるべきだ」「完璧でなければならない」という非現実的な基準を設定してしまうことが原因と考えられます。
英国の国民保険サービス(NHS)の資料では、完璧主義を「自己設定した非常に高い基準を、負の結果が生じても容赦なく追求し、その達成度が自己価値を大きく左右する状態」と紹介しています。(出典:Perfectionism|Camden and Islington NHS Talking Therapies, 最終閲覧日2025-10-27)
この基準が現実離れしている場合、行動が伴わない、あるいは目標を達成できない自分との乖離が生まれやすくなります。こうしたギャップは、自己否定や自己嫌悪という苦しさの主要な要因となり得ます。
失敗を極度に恐れている

完璧主義は、失敗を極度に恐れる心理とも密接に関連しています。
完璧であることを基準に据えると、それ以外はすべて失敗と見なしてしまうため、失敗を極度に回避しようとする思考が働きます。
その結果、「完璧にできないくらいならやらない方がマシだ」という考えに陥り、行動そのものを起こせなくなるのです。
オーストラリアの臨床介入センターであるCentre for Clinical Interventions(CCI)は、過度に高い基準は失敗への不安を強め、回避や先延ばしにつながりやすいと解説しています。(出典:Overcoming Perfectionism|Centre for Clinical Interventions, 2019-10)
失敗をして「自分はできない人間だ」と周囲に思われることや、自分自身でそう認識することを恐れるあまり、挑戦そのものを避けてしまいます。
この失敗を恐れる心理が、行動できない自分と完璧を求める理想との間で矛盾を生み出す大きな原因となっています。
他人の評価を気にしすぎている

「できない人だと思われたくない」「常に優秀でなければならない」といった、他人の評価を気にしすぎることも完璧主義を強める一因です。
前述したNHSの資料では、完璧主義の定義の一つとして、自己評価が、自分の定めた非常に高い基準の追求や達成に強く依存している状態を挙げています。
この自分の定めた基準に、他者からの評価を取り込んでしまうと、結果的に常に他人の目を気にして行動することになります。
他人の評価軸で物事を判断すると、自分のできる・できないに関わらず、完璧であることを演じ続けようとします。
結果として、自分の能力を超えた理想を掲げざるを得なくなり、理想は高いのに現実が伴わないというギャップに苦しむことになります。
能力不足への不安と自己防衛の心理

「自分には、あの人のように完璧にやり遂げる能力がないのではないか」という不安が先立つと、人は失敗を避けるために自己防衛的な行動を取ります。それが先延ばしです。
前述したCCIの資料では、完璧主義がしばしば先延ばしにつながると解説しています。
失敗する可能性のあるタスクを意図的に避けることで、自分はできないという現実と向き合うことから一時的に逃避するのです。
しかし、行動をしなければ経験が積めず、能力は向上しません。結果として、能力不足への不安は解消されないまま理想だけが残ります。
これが「能力が不安だから行動しない」→「行動しないから能力が上がらない」→「ますます不安になる」という悪循環の起点となります。
なお、先延ばしがひどくなる原因や具体的な改善法については、「先延ばし癖がひどい原因とは?完璧主義との関係や改善法を徹底解説」の記事で詳しく解説しています。

オーバーシンキングと二極化思考

完璧主義になってしまう人は、特定の思考の癖を持っていることが多く、その代表的なものがオーバーシンキングと二極化思考です。
オーバーシンキングは、行動する前に「もし失敗したらどうしよう」「このやり方で完璧だろうか」と過剰に考え込み、リスクばかりに目がつくことで、行動が停止してしまう状態を指します。
一方、二極化思考は、物事を完璧(100点)か無価値(0点)かで判断する極端な思考パターンです。
前述したCCIの資料でも、完璧主義の思考の例として二極化思考が挙げられています。
この思考癖があると、80点や90点の結果を出しても、100点ではないから失敗だと捉えてしまいます。
完璧以外の選択肢を自分から奪ってしまうため、行動へのハードルが極端に上がってしまうのです。
- 一つのミスで「すべてが失敗だ」と結論づける
- 目標の90%を達成しても「達成できなかった10%」ばかり気にする
- 準備が完璧でないと行動に移せない
- 常に「こうあるべきだ」という基準で自分や他人を評価する
完璧主義から抜け出すための改善法
- 理想ではなく明確な目的を設定する
- 失敗の許容範囲を広げて行動のハードルを下げる
- 他人軸を手放し自分の評価軸を持つ
- 目標の6割を目指して形にする
- 行動しながら考える習慣を身につける
理想ではなく明確な目的を設定する

高すぎる理想と現実のギャップに苦しむ場合、まずはその自分の基準を見直すことが改善の第一歩です。
完璧にこなすことそのものが目的化していないか、一度立ち止まって考えてみましょう。
重要なのは、その作業の本来の目的に立ち返ることです。
例えば、仕事の資料作成において、上司にプロジェクトの進捗を理解してもらうことが本来の目的であるとします。
その場合、デザインの完璧さよりも、必要な情報が簡潔にまとまっていることの方が重要です。
前述したCCIの資料でも、非現実的な基準を見直し、より柔軟で達成可能な基準を設定することが推奨されています。「完璧さ」という曖昧な理想ではなく、「目的を達成するために最低限必要なラインはどこか」という明確な基準に切り替えることで、不要な完璧さを手放すことができます。
失敗の許容範囲を広げて行動のハードルを下げる
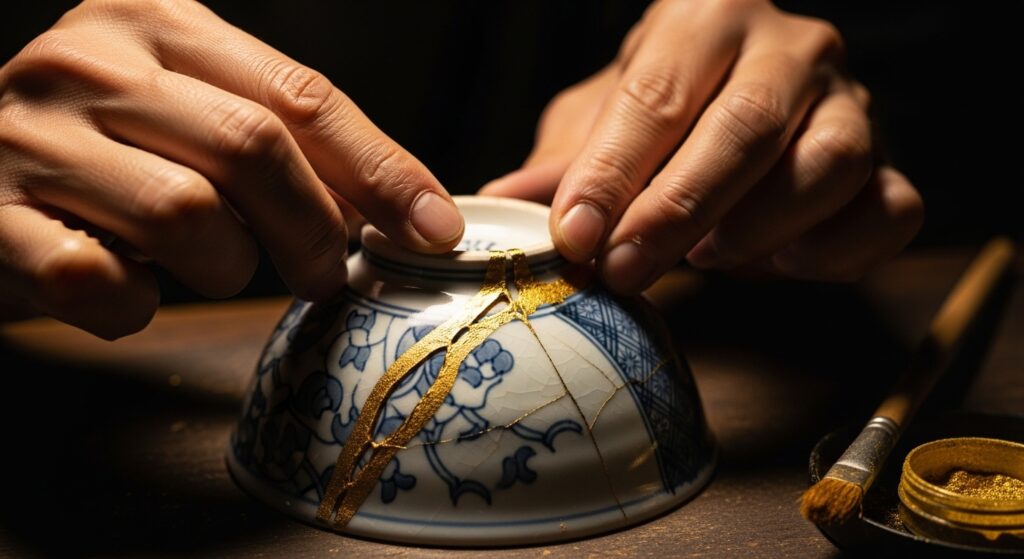
失敗を極度に恐れている状態を和らげるには、失敗そのものに対する捉え方を変えるアプローチが有効です。
失敗は悪いものではなく成功への過程と捉え、学びや改善の機会と考えていきましょう。
前述したCCIの資料では、改善法の一つとして「行動実験」という考え方が紹介されています。
これは、あえて完璧ではない行動を試し、自分が恐れていたほど破局的な結果は起こらないことを意図的に経験するアプローチです。
「致命的ではない失敗はOKとする」「小さなミスは修正すればよい」と、自分の中で失敗の許容範囲を少しずつ広げていくことが、行動への心理的ハードルを下げることにつながります。
他人軸を手放し自分の評価軸を持つ

他人の評価軸に振り回されていると感じる場合は、意識的に評価の基準を自分に戻す必要があります。
他人がどう思うかではなく、「自分が昨日より少し進んだか」「自分が決めたタスクを一つ完了できたか」という自分軸での評価に切り替えていきましょう。
前述したNHSの資料に示されているように、自己評価を他者からの評価に強く依存させることは、精神的な負担を増大させます。
他人の評価は、自分ではコントロールできない不確実なものです。
そのため、他人の評価を気にするのではなく、自分がコントロールできる領域に集中し、その行動自体を評価しましょう。
こうした自分軸での小さな達成感は、自己肯定感を高めるうえでも重要といえます。
なお、自己肯定感を高める方法については、「自己肯定感が低い大人は手遅れ?4つの理由と高める方法を詳しく解説」の記事で詳しく解説しています。

目標の6割を目指して形にする

能力不足への不安から自己防衛的に行動を先延ばしにしてしまう悪循環を断ち切るには、「10割を目指して未完成」よりも「6割の完成」を意識的に目指しましょう。
この6割完成を実践する鍵となるのは、タスクの細分化(ベイビーステップ)です。
前述したCCIの資料に示されている先延ばし対策のセクションでも、圧倒されてしまうような大きなタスクを、管理可能な小さなステップに分解する重要性が解説されています。
例えば、仕事で企画書を作る場合、完璧な企画書を1本作ると考えるとハードルが上がります。
そうではなく、まず6割の骨組みを作ることを目標にします。これにより、行動へのハードルが劇的に下がり、「まず形にする」ということができるようになります。
- テーマに関する資料を3つ探す(すぐできる)
- 構成案(見出しだけ)を作る(6割の骨組み)
- 序論の3行だけ書く(着手する)
- 上司に骨組みを相談する(早い段階で軌道修正)
行動しながら考える習慣を身につける

オーバーシンキングや二極化思考で行動が止まってしまう場合は、思考よりも行動を優先する習慣を身につけることが有効です。
考えすぎて動けなくなっている時は、意識的に行動しながら考える習慣を身につけることが重要です。
前述したCCIの資料で紹介されている行動活性化の考え方を応用し、思考が停止していても、まずは行動をトリガーにすることを試みましょう。
例えば、5分ルールを決めて、「5分考えても答えが出なければ、まずはできることから手を付ける」あるいは「誰かに聞く」と決めておくと、思考のループを断ち切りやすくなります。
行動することで新たな情報が入り、結果として思考も整理されることが多いのです。
| ルールの名称 | 具体的な内容 | 目的・効果 |
|---|---|---|
| 2分ルール | 2分以内に終わるタスクは、見つけ次第すぐに片付ける。 | 小さなタスクの先延ばしを防ぎ、完了の体験を積む。 |
| 5分ルール | 5分考えて分からなければ、まず行動する。(誰かに聞く、分かる所から手をつけるなど) | オーバーシンキングによる行動停止を防ぐ。 |
| タイムボックス | 「10分だけ考える時間」「次の30分は作業する時間」と明確に区切り、作業時間になったら強制的に手を動かす。 | 思考と行動を強制的に切り替え、作業時間を確保する。 |
できないくせに完璧主義になってしまう原因と改善法まとめ
この記事では、できないくせに完璧主義になってしまうという苦しい状態について、その背景にある5つの主な原因と、それぞれに対応する具体的な改善法を解説しました。
この苦しい状態は、多くの場合、あなた自身の能力不足ではなく、「理想と現実のギャップ」や「失敗への恐れ」といった思考の癖が原因となっている可能性があります。
このような矛盾した状態に悩んでいる方は、決して自分一人で抱え込まずに、ご自身の心の健康を最優先に行動することが重要です。まずは完璧を目指す自分の基準を少し緩めることから始めていきましょう。
最後に、ここまでのポイントを振り返りましょう。
- 高すぎる理想と現実のギャップが苦しさの原因である
- 失敗を極度に恐れる心理が行動を停止させる
- 他人の評価軸を気にしすぎると理想が高くなりすぎる
- 能力不足への不安が自己防衛的な先延ばしを生む
- オーバーシンキングと二極化思考が完璧以外の選択肢を奪う
- 理想ではなく明確な基準に切り替えることで不要な完璧さを手放す
- 失敗の許容範囲を広げて行動のハードルを下げる
- 他人軸を手放し自分がコントロールできる行動を評価する
- 目標の6割を目指して形にすることを優先する
- タスクを細分化しベイビーステップで着手する
- 行動しながら考える習慣を身につけて思考停止を防ぐ

よくある質問
完璧主義は悪いことですか?
いいえ、すべてが悪いことではありません。完璧主義には、目標達成の力になる良い完璧主義(適応的完璧主義)と、自己否定や行動停止につながる悪い完璧主義(不適応的完璧主義)があります。
できないくせに完璧主義になってしまうのは甘えでしょうか?
甘えではなく、失敗への強い恐れや完璧でなければ価値がないという思考の癖が原因であることが多いです。
完璧主義をすぐに改善する方法はありますか?
思考の癖をすぐに変えるのは難しいです。まずは「100点でなくても完了させる」という小さな行動の変化を意識することから始めるのが現実的な改善法です。

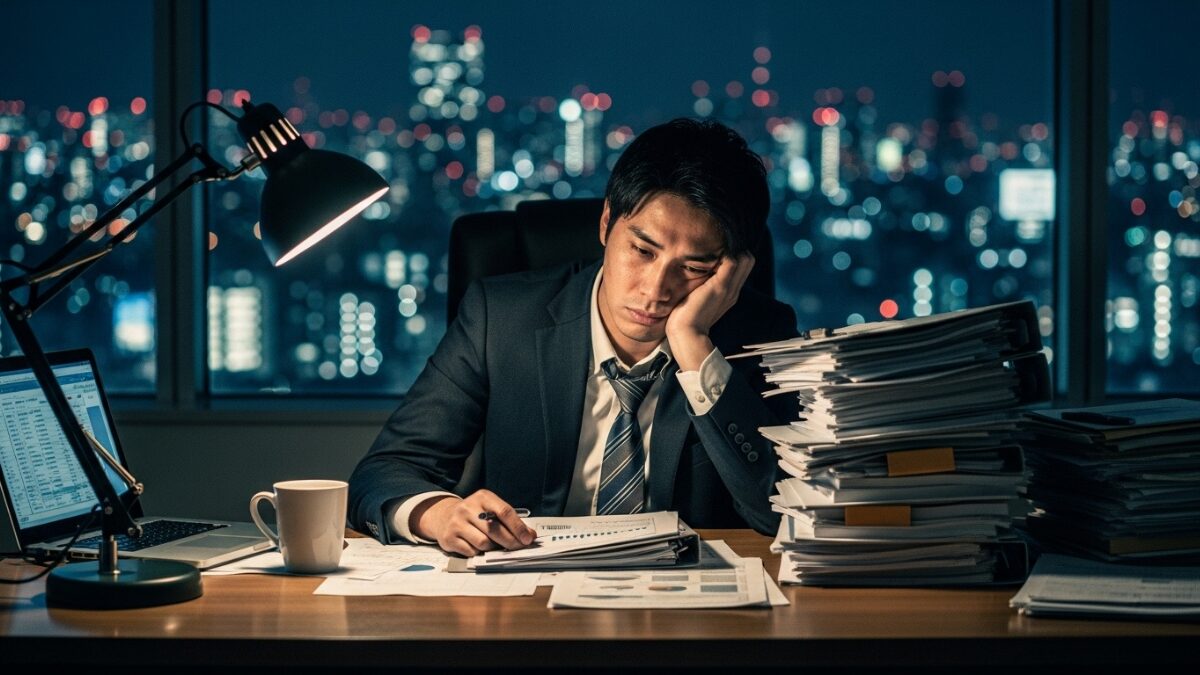
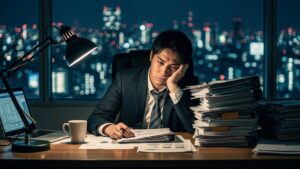
コメント